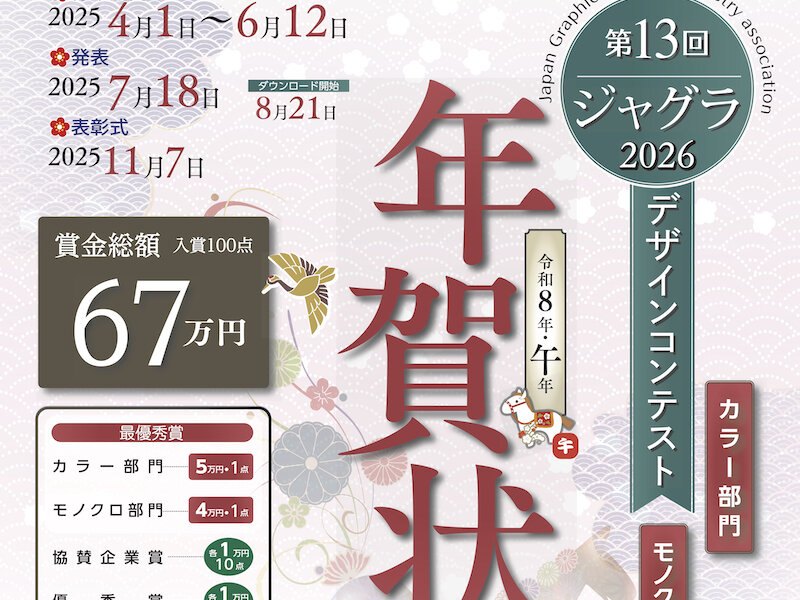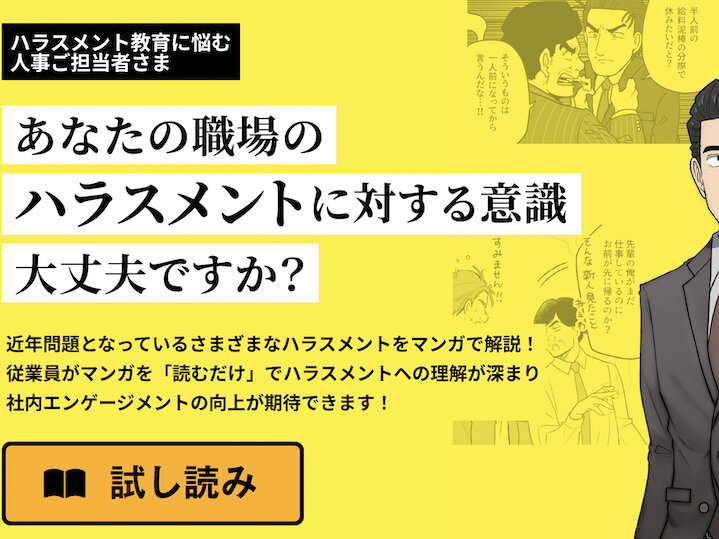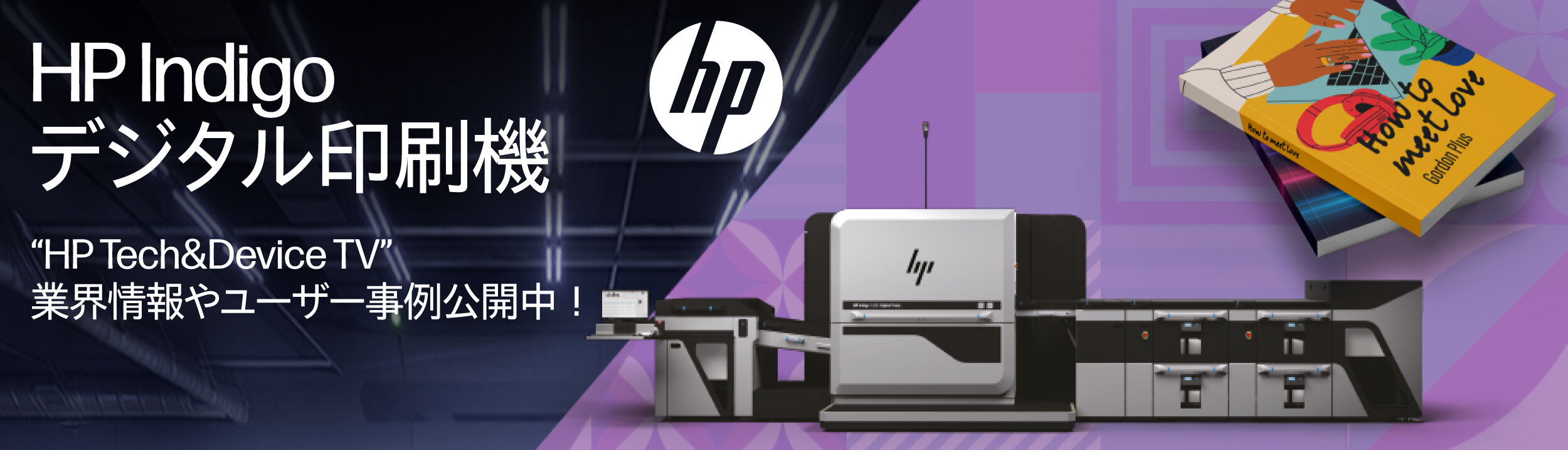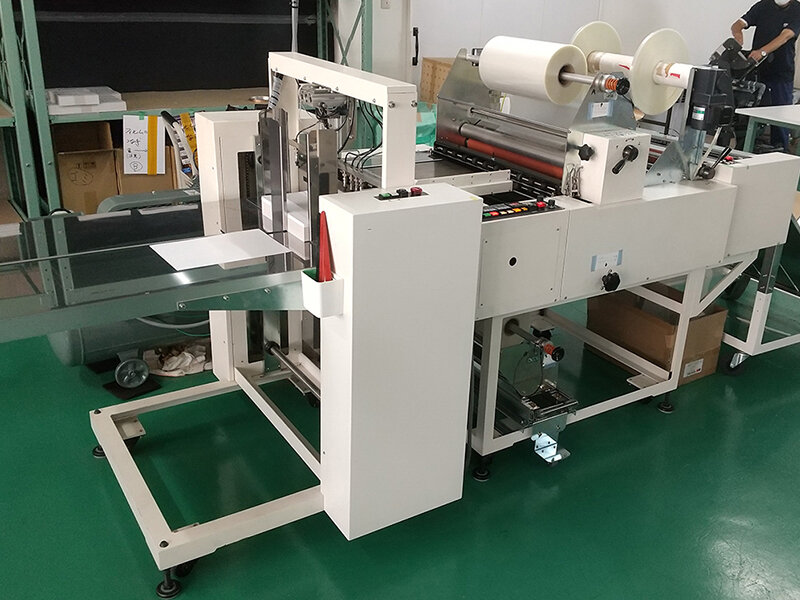製本業界の現状と課題、明るい未来とは
全日本製本工業組合連合会 田中 眞文 会長 インタビュー
「魅力」ある製本業界へ
コロナ禍による印刷業界の厳しい状況は、そのまま製本・後加工業界に影響を与える。製本加工賃は数十年前から変わらないなど、厳しい状況の企業も多いが、製本・後加工業には、フィニッシングの専門家として、印刷物の付加価値を高めるための豊富な知識とノウハウがあり、今後も印刷業界の最大のパートナーであり続けることは間違いない。また、昨今は製本業界が紙製品を開発して、ECサイトなどでBtoCの展開を図るケースも珍しくなくなってきた。長引くコロナ禍の中、製本業界は引き続き印刷業界を最大の取引先としながらも、出版社やその他の業界への市場創出に努力している。そこで今回、全日本製本工業組合連合会の田中眞文会長にコロナ禍における製本業界の現状と課題、そして製本業界の明るい未来に向けた展望などについて話を聞いた。

書籍は比較的堅調、雑誌は底を打たない厳しさ
2021年末現在で全製工連の組合員数は650社を下回る推移となっており、廃業を中心に4%強の減少が続いている。
品目別に見ると、雑誌は底を打たず厳しい。報道されているように、昨年はコミックスを含む月刊誌が発行高4.5%減、週刊誌は同9.7%減、2020年はコロナ禍で定期誌の刊行延期や中止が相次いだが、2021年はそれは無かったものの、部数減による紙媒体からWebへの移行や休廃刊が止まらない。コミックスは2020年夏〜昨年冬にかけて大ヒットした「鬼滅の刃」が一段落し、それに代わっていくつかのタイトルがヒットしたが、トータルでは微減した。
一方、書籍はすべてのジャンルが良いわけではないが比較的堅調で、紙での発刊分が15年ぶりに2%程度の増加。牽引しているのが、教科書・学参・語学・資格書など勉強の本と絵本を含む児童書と文芸書。これを見ると、いかに一般社会人が本を買わなくなってきているのかが分かる。出版市場の28%が電子となり、存亡の危機に立たされている仲間が多い。
加えて、労務費だけでなく物流費や材料費、加工費の上昇圧力が大きく、先日も出版社の団体に対して印刷工業会と連名で現行の窮状への理解を求める文書を提出したところである。また、大手が商社と組んで検討しているICタグ装着によるDX化の推進など、周辺環境も目まぐるしく変化しており、業界ぐるみの対応を検討していかなければならない課題も増えてきている。
強弱分かれる商印製本
また、商業印刷製本はコロナ禍も3年目となり、初年度より状況は改善している側面もある。足元は繁忙期に向けて動きは良くなっており、ボリューム感も戻っているものもある。一方、商印内でも強弱が分かれてしまっており、大ロット案件が増加し、小ロット案件はむしろ消失している傾向が見られる。オンライン開催の影響を受けるイベント関連、観光、飲食はより厳しく減少。通販関係のマニュアルやチラシなど、特需的な動きは継続している。
紙製品、文具関係は苦戦
紙製品関連はコロナ禍の長期化、オンライン開催の浸透により、動きも鈍く種類および部数の減少傾向が続いている。イベントの開催がないため、企画自体が消滅、動かない影響が大きい。今シーズンはカレンダーが終わり、新学期に向けて学参関係に取り組んでいる。
文具関係は、春に向けた新製品が動いているが、色や柄のバリエーションが減ったり、再販売が発生しなかったり影響が出ている。ミシン掛けノートなど、希少な技術分野は忙しいようだ。
別製、販売用ともに手帳は10%減
手帳は大別して別製手帳(年玉手帳)と販売用手帳がある。別製手帳は新型コロナ感染症のため、自宅におけるテレワークの増加により、手帳の使用が減少したり、SDGsの観点から手帳の製作数を減らすなどの諸要因により10%ほど減少すると考えている。
販売用手帳は、発売元がコロナ禍の業績を考えたり、返本率を低下させるために商品別の生産数は10%ほど減少すると考えている。キャンペーン・イベントなどが対面からネットなどを通じた非対面型が中心になり売上が減少している。
そのような中、先日の「じゃぱにうむ2022」での発表であったように、田中手帳さんの手帳製本技術を応用した新しい取り組みは特出すべきと考える。