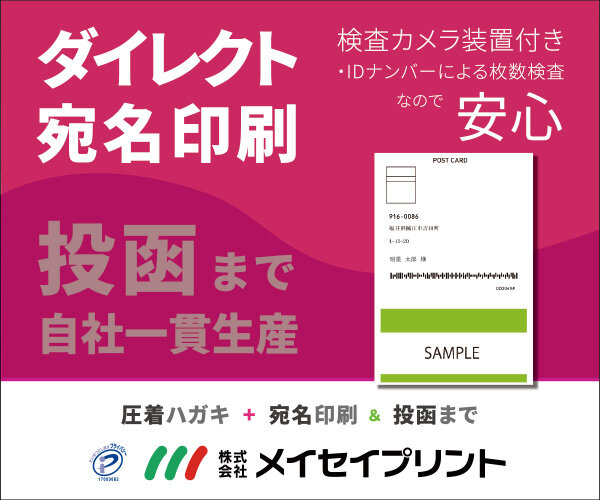研美社、「タッチ1秒」名刺交換〜相手のスマホにパーソナル情報を送信
非接触ICカード名刺「スマートニアバイ名刺」
相手のスマホに非接触ICカードをかざすだけで、自分のパーソナル情報を相手のスマホに送信できる画期的なサービスが誕生した。プラスチックカード印刷の(株)研美社(本社/大阪市都島区、中田逸郎社長)が昨夏に開発、page展で印刷会社の営業ツールの1つとして提案する。この「スマートニアバイ名刺」を使えば、従来のように紙の名刺を手渡しする必要がなくなり、SDGsにも寄与する。令和時代の新たな「名刺交換」のシステムとして将来的な普及が期待できそうだ。

今や誰でもスマホを持つ時代。LINEの友達追加にしても、QRコードにスマホをかざすだけで簡単に行える。しかし日本のビジネスの世界では、いまだに紙の名刺を交換する慣習から抜けきれない。「DX」があらゆる業界で叫ばれ、名刺入れから紙の名刺を取り出して「いやー、どうもどうも」と名刺交換している時代ではないはずなのだが、名刺交換の「DX化」はまだまだ遠い先のように思われる。
研美社が今回のpage展で提案する「スマートニアバイ名刺」は、印刷業界において「印刷DX」が叫ばれる中においても、DX化がなかなか進まない日本の「名刺交換」の常識を塗り替えるサービスと言える。「スマートニアバイ名刺」の発案者である同社の彼谷佳彦取締役は「米国では、すでに若者を中心に『スマートニアバイ名刺』のようなサービスが一般的に普及している。当社はプラスチックカードに特化した印刷会社であることが特長だが、今の世の中の流れを見たとき、デジタル系のコンテンツの商材が今後の生き残りには不可欠だと考えていた。そこで当社の強みを分析&再確認し、改めて強みを生かすことができる商材を考えたとき、『スマートニアバイ名刺』というアイデアに辿り着いた」と話す。
自社の強みとして再確認したのは、他社にないプラスチック素材の仕入れルート、インクジェット印刷機を用いたバリアブル印刷、IDカードの通販事業で培ったネット販売のノウハウなどである。そして、その強みを掛け合わせ、内製で一気通貫できるサービスとして開発したのが「スマートニアバイ名刺」であり、まさに同社の長年にわたる技術ノウハウが凝縮されたアイテムと言えるだろう。
9つのコンテンツをワンタッチで起動・閲覧
「スマートニアバイ名刺」に情報掲載するコンテンツは、電話、メール、HP、所在地、地図、各種SNSなど。9つのコンテンツを掲載することが見た目にも「スマート」であるようだが、要望によりカスタマイズも可能となっている。
「ブティックを経営している女性の経営者は、『スマートニアバイ名刺』の機能をショップカードとして活用しており、オンラインショップのコンテンツを載せているほか、インスタやFacebookなど、SNS系を中心に情報掲載している。これまで、顧客にはそれぞれのQRコードを読み込んでもらっていたようだが、スマートニアバイ名刺の機能を使用することで、その煩わしさがなくなり楽になったと喜ばれている」(彼谷取締役)

名刺交換した相手のスマホにかざして送信したパーソナルデータは、相手側により「保存」してもらう作業が必要になるが、同社営業部の宇野伸弥本部長は「スマホのトップ画面にアイコンのように保存してもらうのが最も効果的。スマホ画面には顔写真が出るようになるのだが、何回も顔写真を見ていると愛着が湧いてくるという効果が研究により明らかになっているようで、営業マンにおすすめのツール」と説明する。とくに、車や保険、不動産など、長期間にわたり何回も顧客とやりとりを行う業種に推奨しており、「これらの業種の顧客を持つ印刷会社には、ぜひとも『スマートニアバイ名刺』の代理店になっていただきたい」(宇野本部長)と話す。
印刷業界に「スマート名刺」を自社の営業ツールとして活用してもらうことが、今回のpage展の出展目的である。
1ヵ月/800円で無制限に利用可能
「スマートニアバイ名刺」の利用価格は1ヵ月800円。これを高いと思うか、安いと思うのかは人によると思うが、「紙の名刺ではないので、例えば1ヵ月に1万人に送信しても800円。また、紙を消費しないので、SDGsにも貢献する取り組みとなる」(彼谷取締役)。
同サービスを利用した場合、今は過渡期の真っ只中であるため、紙の名刺と併用することになる可能性が高いが、他社に先駆けて「名刺DX」を推進する企業としての取り組みは、営業活動においてもプラスのイメージになることは間違いないだろう。同社においても、「大手企業や大切な取引先の方と挨拶するときほど、逆に『スマートニアバイ名刺』だけで名刺交換することに挑戦している。これにより、先進的な企業であることをアピールしている」(彼谷取締役)ということだ。
昨夏から販売を開始し、現在のユーザーは30件程度だが、2022年中には1万人のユーザー獲得を目指す。間違いなく、今回のpage展における注目コンテンツの1つであると言える。