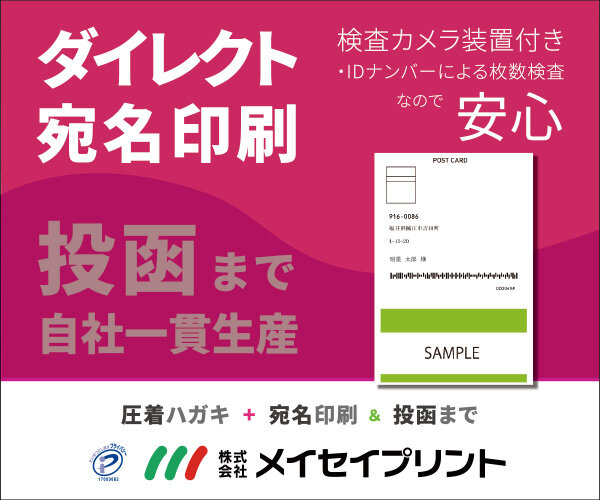トップインタビュー|ミューラー・マルティニジャパン 五反田隆代表に聞く
「非生産時間」を減らす機械
工業的生産体制の構築へ 〜 自動化・見える化と品質保証
働き方を変える機械
昨年7月、本社内でオープンハウスを開催し、「人手不足」や「働き方改革」などの課題解決に向けた自動化、省力化、品質管理ソリューションの一端として、全自動中綴じ機「プリメーラMC」を中心とした自動化ラインとワークフロー「コネックス4.0」の有効性を実証するセミナーとデモを実施。実演では、多彩な品質管理機能をはじめ、オートローダーとスタッカー後の自動紙バンド結束およびフイルムラッピングのインライン接続を紹介した。その後、オートローダーと自動紙バンド結束装置は、印刷通販会社などへの納入が進んでいる。2020年も依然として人手不足は続き、むしろ慢性化しつつある中で需要はあると考えている。
「人手不足」や「働き方改革」に対してメーカーができることは、「品質保証ができる機械の提供」と「自動化による生産効率向上」になるわけだが、「不測の事態」が多い製本現場では、その効果をシミュレーションしにくいというのもひとつの障壁になっている。「新しい設備を導入して生産性が30%向上した。その分、就業時間を30%削減できれば残業をなくせる」、そんな計算が単純にできないのが製本工程である。そこには経営者の「オペレータをハッピーにするための設備投資」という認識や考え方が必要である。
「需要低迷」「小ロット化」「人手不足」「時間外労働の上限規制」といった様々な問題を抱える中小印刷製本会社において、設備投資によってその打開策に打って出る会社と、利益が出ないことを理由に設備投資を控える会社。今後、明暗を分けるように思う。
老朽化した機械で溢れる市場
2020年も、これら背景のもとで、「自動化による生産効率向上」の提案が当社の大きな柱になるが、これだけ既設機の更新がない中で、30年、35年と、かなり老朽化した機械が市場に溢れており、これらはいつ壊れてもおかしくない。我々の製本機ビジネスとは直接関係はないが、新聞社でもオリンピックのタイミングで設備を更新するケースが多かったものの今回はほとんどない。つまり「延命」である。製本機も同様、設備更新のサイクルが長くなっており、そのリプレイスの提案もひとつの切り口になるだろう。
また、製本工程の「見える化」も重要な施策のひとつ。ワークフローで繋がって一気通貫の流れになる、これも大事なことだが、このジョブがお客様の工程の中で「どこにあるのか」を共有することが最も重要であり、そこでムダも見えてくる。印刷なのか、製本なのか、発送中なのか。この情報は従来、ほとんどが現場、工場ベースのシステム内に留まっている。その中でどこかにトラブルが生じても、それが上層部に伝わるには時間がかかる。ましてや工場と営業所が別ならば、営業所の人にはその情報が入らず「今日やっているはず」ということになる。その実現には、機械側から見える化に必要な情報を発信する必要がある。当社では、JDF・JMFを介して、お客様の生産管理の中に機械が発信した情報を組み込むことができる。これがワークフローの中でも重要なポイントを占める。
drupaはデジタル中心
さて、今年はdrupaイヤーだが、ミューラー・マルティニの出展は、ブックオブワンやバリアブル製本など、デジタルが中心になることは間違いない。これらの無人化に向けた提案も出てくるだろう。現在、日本の市場ではまだまだハードルの高い提案になるかもしれないが、その起爆剤となるのはやはり出版社になると思われる。ミューラー・マルティニでは、「インダストリアル・マニュファクチャリング」という言葉を使っている。これは「手工業ではなく、工業的に本を作り出す」という意味。前述のように、バレオ1台ではビジネスにはならない。そこに工業製品を製造する仕組みが必要であり、ミューラー・マルティニは、それを支える製本機械を提供している。
また、drupa2020には、無線綴じ機および中綴じ機で、さらに切り替え効率を高めたソリューションも出てくるだろう。ただ、以前のように「1時間を15分に短縮」といったドラスティックなものではなく、「5分を3分に短縮」といったものになるため、そこにお客様が魅力を感じるかどうかは疑問であるが...。
昨年は、自動化や見える化など、メーカーのソリューションとユーザーが迫られている人手不足や働き方改革に対する向き合い方に多少のギャップがあった1年だったように思う。drupaがそのギャップを埋めてくれることを期待している。
なお、drupa2020の出展情報は、1月半ばあたりから徐々に出てくる。4月上旬にはその全貌をお伝えできると思う。ご期待願いたい。