トップインタビュー|ミューラー・マルティニジャパン 五反田隆代表に聞く
「非生産時間」を減らす機械
工業的生産体制の構築へ 〜 自動化・見える化と品質保証
「『働き方を変える機械』という視点から機械づくりを考えるべきだ」と指摘するミューラー・マルティニジャパン(株)の五反田隆代表。岐路に立つ印刷製本産業において、「働き方改革」と「人手不足」という大きな課題が浮き彫りになる中、「自動化」「見える化」「機械の信頼性(品質保証)」といった3本柱で「製本機械に求められること」「製本機械メーカーとしてできること」を追求している。今回、drupaイヤーの幕開けに際し、業界の現状と課題、それに対する同社のソリューションについて聞いた。
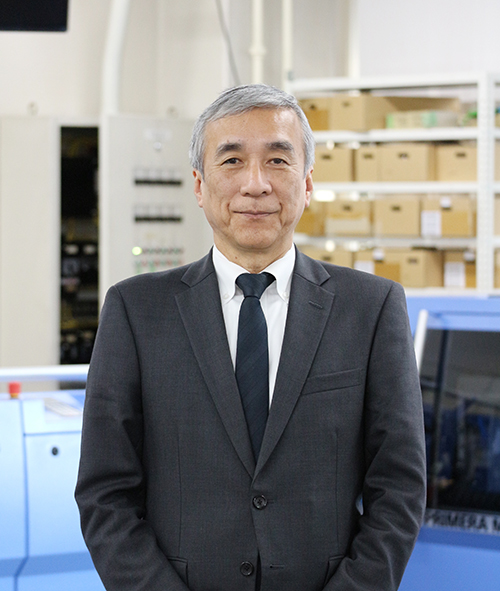
人をコストとして捉えられるか
まず、当社の昨年の販売実績からお話しすると、無線綴じ機、中綴じ機ともに、おかげさまで当初の計画を達成し、市場の状況から見ると「健闘」といったところである。
とくに昨年は、製本専業会社というよりは印刷会社からの引き合いが多かった年だった。この傾向の背景には、製本工程単体での効率化を模索するというより、印刷物の製造工程全体を最適化することで生産効率を向上させようとする動きが顕著に表れている。印刷工程で生産効率を上げることに成功した印刷会社が、手つかずであった製本工程の改善に着手し、一連の工程の中で効率化を考える段階に入っている。今後は、印刷会社と製本会社、あるいは不得手部分を互いに補完し合うような企業統合や吸収合併も進み、産業構造に変化をもたらす可能性もある。また、これを違う角度から見ると、印刷と製本はもっと密な関係を築いた中で、互いにロスをなくし、トータルで効率を上げていくための取り組みを進める必要性もあると感じている。
分野別で見ると、製本専業の主要な得意先である出版関係が弱含みである。とくに、低迷する雑誌の多くを手掛ける関東地区は厳しい環境下にあると言える。この場合、製本工程は基本的に「受け」「待ち」の仕事。そこで製本単体で生産効率を上げることは難しい。
出版分野全体では「底打ち」という見方もあるが、傾向として「タイトル増、ロット減」は顕著である。その中で「どこで製造コストを抑えるか」となると、まだまだ人海戦術的な要素の強い製本工程において「人件費」が有力候補に挙げられる。ただ、製本会社が「人をコストとして捉えられるか」である。製本会社は比較的保守的であるのに対し、印刷会社の方が改善意識は高い。前述の通り、印刷物製造をトータルで考えやすい環境にもある印刷会社では、市場の現状や課題に対し、「設備投資で打開する」という考え方に繋がりやすいのかもしれない。
「小型機による分散生産」の可能性
小ロット化がますます進む中で、生産性を上げるための設備投資を考えた場合、言うまでもないが、それは機械の回転数ではなく、仕事の切り替え時の「生産されない時間」を減らす機械であり、そこが新たな設備投資のポイントになる。
昨年、当社が納入した無線綴じ機はすべて最高7,000冊/時の「アレグロ」である。設備更新に際し、1万冊/時以上の高速機には、現状でほとんど引き合いはない。つまり、今後は1万冊/時以上の高速機で利益を出すことは難しいということ。やはり切り替えの早さが焦点になる。これは無線綴じ機における傾向として顕著に表れており、現状の市場に対する効率化に向けた設備投資として、モーションコントロール技術を搭載した「アレグロ」が選ばれている。
世界的にも同様の傾向が見られるが、欧米での設備投資はさらにダウンサイジングしたものになっており、生産スピード1,500冊/時の「バレオ無線綴じ機」と三方断裁機「インフィニトリム」のラインで、1冊ずつサイズや厚みの異なる本を連続生産する「ブックオブワン」が中心になりつつある。
我々機械メーカーのバインダービジネスは小型化が顕著だが、しかしこれ単体では利益は出ないし、ビジネスにはならない。デジタル印刷機とのライン化による連続生産や無人化などの工夫がなければ「ブックオブワン」を現実的な価格で製造・提供することはできないからである。
そこで新たな収益モデルとして出てきたのが「複数の小型の機械で、しかも分散した場所(工場)で生産する」というもの。とくに米国で進んでいる。当社が提唱するフィニッシング4.0の製品群は、この分散型生産方式に対応している。
日本でもそう遠からず、このようなビジネスモデルが生まれるように思う。そうなると設備は小型になり、実際、米国ではこのようなマルチサイト運用の会社にバレオの導入が進んでいる。例えば書籍ならば、東京で制作したプリプレスデータを各拠点に送り、そこで印刷、製本し、同日に全国の書店に並ぶ。おそらくこの形は出版社が中心となり、各地方の印刷製本会社に委託する形で進めるのが現実的だと思う。
一方、世界的にも高速機はそのまま使用され、残るだろうと言われており、古い高速機と切り替えが早い新しい小型機の共存の状態が続くと見ている。つまり、極端な話、我々のビジネスは切り替えの早い効率機の訴求をメインとし、高速機に対してはサービス、いわゆる「延命」ということになる。












































