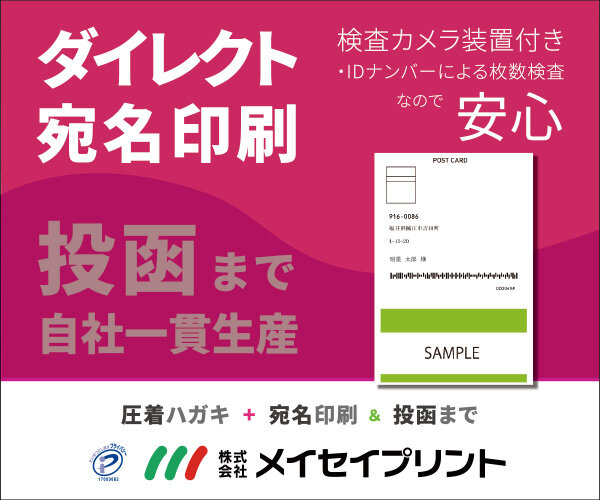トップインタビュー|ハイデルベルグ・ジャパン、ヨルグ・バウアー社長に聞く
技術と創造力で印刷業界を支援 〜 お客様のために最善を
ハイデルベルグ・ジャパン(株)(本社/東京都品川区)の新たなリーダーとして昨年11月1日、ヨルグ・バウアー氏が新社長に就任した。新しい元号「令和」を迎えた2019年、インダストリアルインクジェット機「プライムファイア106」の国内1号機の導入や、新たなビジネスモデルである「ハイデルベルグ サブスクリプション」の国内初導入など、バウアー社長は、日本の印刷業界に対し、新たな可能性への挑戦を提唱してきた。そこで今回、バウアー社長に、日本の印刷産業の現状や抱えている課題、そしてそれら課題を解決するハイデルベルグの取り組みなどについて聞いた。

──来日当時に感じた日本の印刷産業の印象(欧州をはじめ世界市場との相違など)について。
バウアー 印刷会社とクライアントとの関係、またサプライヤーとの関係も違うと思う。共通点としては、受注してから印刷までの基本的な生産は同じだ。
相違点としては、日本の印刷会社は、クライアントから生データを受け取っていること。そして、印刷会社が、印刷用のPDFを準備している。大変厳しい価格競争の中では明白な利点と言える。
通し枚数については、年間を通して、どの機械も低い。欧州では24時間稼働の機械が多い。さらに日本は、営業の人数が多いことも特徴と言える。
欧州ではMIS(既製品)は標準で、また、MISと生産の間がJDFもしくは、XJDFで統合されている。欧州では、よりプロセスが標準化(より少ない例外、より少ない人依存)されており、自動化が容易だと思う。
欧州のオーナーやトップマネジメントは、ITや製品の受注から出荷までのワークフローにフォーカスしているのではないか。例えば、ドイツの印刷会社では、オーナー自身がビジターに対し、クライアントと関わる部分から管理、生産、ビジネスモデルまで、自分ですべてを説明することができる。
──現時点における日本の印刷産業の課題、進むべき方向性など。
バウアー まず、最初に言わなければいけないのは、品質とクライアントのビジネスにフォーカスしたいということ。印刷はサービス産業である。日本は、多くの会社が世界規模で、この方面でリードをしている。しかしながら、平均をとると、多くの面でグローバルの平均以下ではないかと思う。
もちろん、これはすべての印刷会社に当てはまるわけではないが、ちょっとドラスティックな言い方をすると、受注から最終製品の出荷まで、本当のデータの統合、自動化ができていない。ゆえに部数が極端に少なくなり、仕事の数が増えると、余分な手作業が増え、ミスや間違った情報の入力などのリスクが増加する原因になっている。
さらにオペレータやマネージャーは、習慣にしがみつこうとしている。これはどこの国でも一緒だが、日本はそれがちょっと強いようにも感じる。それゆえに新しいワークフローや機械を導入しても、同じ仕事のやり方をしたがる。結果的に新しい投資から最高の結果を得られていない。