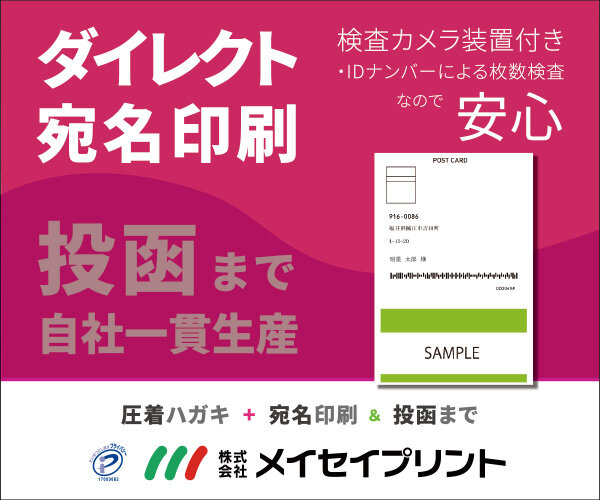モリサワ、「印刷・出版」に軸足、コア技術活かして新市場へ
新たなブランド戦略へ 〜 台湾、韓国、米国の海外事業も本格化
「基盤ビジネス」と「成長ビジネス」
第二期中期計画における重点事業は、基盤ビジネスとして「モリサワパスポート」「MC-Smart」「MVP」「印刷関連 資機材販売」の4事業、成長ビジネスとして「フォントOEM」「TypeSquare」「MCCatalog+」「電子書籍」「海外事業」の5事業がある。
【基盤ビジネス】
▽モリサワパスポート
現在の契約の伸びは一般企業中心の新規市場における増加が寄与している。「『今後、どのような付加価値を提供するべきか』については、第3期中期経営計画の重要な課題になる」(森澤社長)
▽MC-Smart
写植の時代から培ってきた組版技術を投入した専用ソフト。アドビインデザインなど汎用DTPソフトの機能向上で市場の寡占化が進み、かつてのような出荷台数は見込めないものの、バッチ処理や学参関連の組版での処理能力の優位性、導入後の手厚いサポート体制などに高い評価を得ている。「ニッチ市場だが、顧客の声に耳を傾けながら新たな方向性を探っていく」(森澤社長)
▽MVP
可変印刷ソフト。小規模のバリアブル印刷にマッチした商品として中小印刷会社やプリンターメーカーから支持を得ている。「今後はクラウド展開なども視野に入れ、新たなサービス展開の機会を広げられるような製品にしていく」(森澤社長)
▽印刷関連 資機材販売
収益基盤として重要な位置付け。
【成長ビジネス】
▽フォントOEM
モリサワフォントのブランド力が通用しない組込み市場に向けて訴求力のある開発を進め、以下の3点の製品や市場開発を進める。
(1)中国語認証ビットマップフォント
中国市場で販売する機器に搭載するフォントは、中国政府の認定機関であるCESIが認定した中国語フォントを購入するしかなく、基本的に中国のフォントメーカーに依存した状態にったが、昨年同社はモリサワが制作したオリジナルの中国語フォントの認証を取得することに成功した。
「従来、日本企業が中国向けに販売する機器の企画や開発、製造にあたっては、中国政府認証フォントの入手に大きな手間や費用が掛かっていた。当社がオリジナルの認証フォントを提供可能になったことで、国内企業は中国向けの組込みビジネスで、かなりのアドバンテージを得ることができる」(森澤社長)
(2)車載関連機器への拡販、研究開発
今後、従来のカーナビゲーションシステムに留まらず、コンソール(各種車載パネル)内で表示されるフォントに要求される機能や品質が多様化するものと考えられる。同社はユニバーサルデザインフォントや、輝度や照明の変化でフォントウェイトを変化させる実証実験を含めた機能開発をグループ会社のリムコーポレーションと連携して継続し、自動車産業に製品や部品を供給するメーカーへの訴求力を高めていく。
(3)MORISAWA App Tools
現在、組込みフォントの分野でもっとも成長の著しいのが携帯端末向けのアプリ市場。ゲームソフトに代表されるこの分野では、企画から調達に至るスピード感が最優先されるため、個別契約に時間を掛ける従来の組込みビジネスのスキームが通用しない。
そこで同社はアプリ業界から要求される仕様許諾の内容を、予めエンドユーザーライセンスに盛り込んで定型化し、従来契約書の作成に要していた時間を不要とする「MORISAWA App Tools ONE」を昨年10月にリリース。モリサワパスポートのノウハウを取り入れ、PC1台あたり7万2,000円/年でモリサワフォント341書体が利用できる。すでに大手ゲームメーカーを中心に、多数の引き合いを受けている。
▽TypeSquare
Webフォントサービス。「将来のWebを支える標準技術になることは間違いないと確信し、今後も注力する」(森澤社長)
市場への訴求ポイントとしては、まず「ブランドイメージの向上」がある。高級ブランドメーカーや、大手メーカーを中心に、広告物で使用する書体を厳格に定めている企業が多い。これまで閲覧するPCに入っているフォントごとに表示イメージが変わってしまうWebサイトでは、ブランドイメージやその世界観のコントロールは困難だったが、TypeSquareを利用することでPCに入っているフォントに依存することなく、印刷物のイメージと同じ書体でWebサイトを見せることができるようになる。
2つ目の訴求ポイントは「デバイスの多様化への柔軟性」。従来のようにフォントを画像化してWebサイトを作成している現状は、PC、スマホ、タブレットなど、表示画面のサイズが異なるそれぞれのデバイス用にデータを用意する必要があり、時間と手間を要していた。すべての文字情報をテキストで保有するTypeSquareであれば、デバイスの差異にも柔軟に対応することができ、制作コストを大幅に軽減できる。
3つ目の訴求ポイントは「アクセシビリティの優位性」。文字情報をテキストで持つことができるということは、検索時の優位性が高くなる利点がある。これに加え、視覚障がい者が必要とする読み上げ機能に容易に対応させることが可能。今年4月に施行された「障害者差別解消法」により、とくに自治体においては視覚障がい者に対して「合理的配慮」が義務づけられることになった。これらの法規制や指導は、将来一般企業にも波及することが予想され、すべての人に公平な社会を実現するユニバーサルデザイン推進の観点からも、Webフォントの優位性が注目されることが期待される。
▽電子書籍
電子書籍の業界はアマゾン(キンドル)のサービスに代表されるように読み放題サービスが主流になってきており、単体コンテンツで直接利益を上げにくい状況になっている。「これまで比較的順調に伸びてきたと思われるビジネススキームが、この先はどう変化するかの見通しが立たない不透明な状況が続く」(森澤社長)
電子書籍による収益のひとつが「MCMagazineによるNewsstand定期購読アプリ」である。5年前からMCMagazineの販売を開始し、現在ではNewsstand販売中の全505誌中199誌(2016年11月現在)で採用されている。これはNewsstand全体の約4割となり、他社に比べて圧倒的なシェアを獲得している。
「年間でのロイヤリティ収入を得るストックビジネスであり、安定した収益を確保できるので、これからも慎重を図りたいところだが、読み放題サービスの拡大によりこれから先は頭打ちの傾向が出てくるのではないかと予想している」(森澤社長)
▽MCCatalog+
電子書籍開発で得た技術を横展開、応用したビジネス。事業の開始時はクライアント(コンテンツホルダー)と印刷会社をMCCatalog+でつなぐビジネスプランを計画したが、東京オリンピックに向けて社会情勢がインバウンドに傾倒しはじめたことや、「障害者差別解消法」の施行などが同時期に始まったことで、自動翻訳機能やポップアップ機能、自動読み上げ機能の強みを活かし、当初の狙いとは異なったターゲットに絞り込んだ販促活動を展開している。
(1)各省庁のインバウンド施策と連携
2020年東京オリンピックに向けて、訪日外国人向けのサービスを経済産業省、総務省がそれぞれ計画し、国内各地域で「おもてなしICTプロジェクト」として実証実験を開始する。そのプロジェクトで、集合型情報アプリであるMCCatalog+が採用アプリのひとつに選ばれ、これから始まる実証実験に採用されることになった。
(2)自治体への販促活動
「障害者差別解消法」の施行により各自治体は、地域の障がい者に向けて合理的な配慮をともなうサービスの実施が義務づけられた。そこで同社はMCCatalog+で広報を住民に配信するサービスを提案。また最近では外国人の居住者を多くかかえる自治体が増えており、自動翻訳機能も評価につながっている。
(3)個別対応OEM版
携帯端末上のアプリである「カタポケ」はあくまでも集合アプリなので、他社のコンテンツ情報もその中に含まれている。企業が消費者向けに行うサービスや、閉ざされたグループ内での運用では集合アプリは使いにくいため、単独利用ができる個別OEM版への対応も始めている。